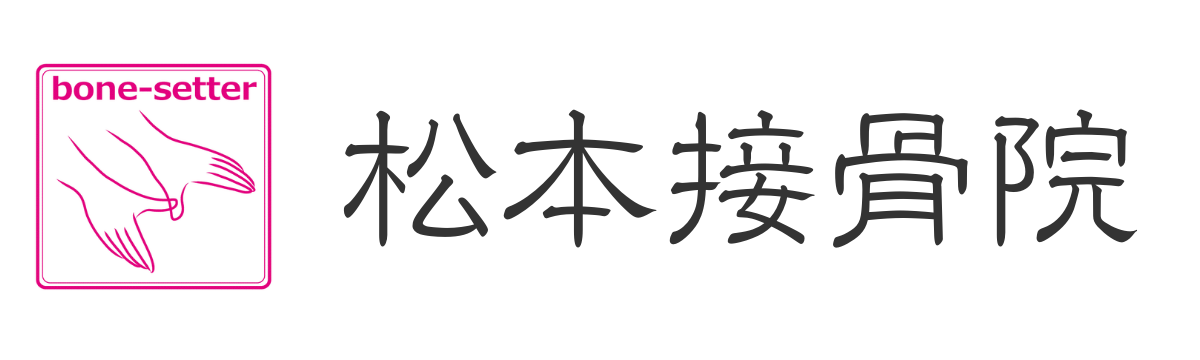食品があふれる時代の悩み
昔は、食品の選択は簡単でした。
目にすることのできる食品は、ほぼ自分が住む地域のそばでとれるもの(もちろん養殖はなく、天然もの)だけでした。
加工食品の種類も多くはなかったからです。
食品の目利きは予算が許す範囲で、より新鮮な物、おいしそうなものを選ぶ目があれば良かったのです。

現在はどうでしょう?
魚介類は養殖があたりまえ、肉や魚は冷凍され、加工されて世界中から運ばれてきます。
野菜やくだものといった生鮮食品でも、韓国や中国、アジア諸国からはもちろん、はるか太平洋を渡ってオーストラリアや南北アメリカ大陸からも運ばれてきます。
日本食代表のお米は、全国のブランド米をはじめ、いくつものクラスの米、玄米、胚芽米、分づき米、さらに最近では洗わなくても炊ける無洗米など、じつに多くの種類が出回っており、有機米、無農薬米も含めたら、どれを買ったらよいか悩みます。
加工食品にいたっては、もう無限と言っていいほどの種類があふれかえっています。
いったい何を基準にして、毎日の食卓にのせる食品を選んだらいいのでしょうか。
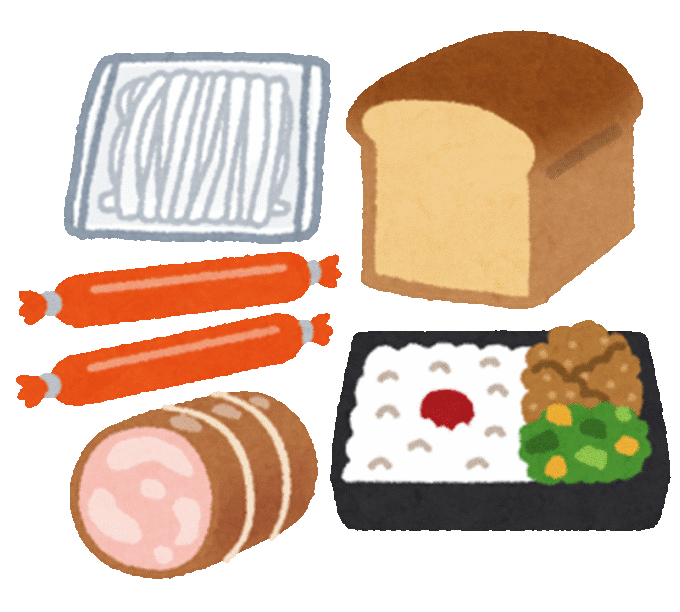
自分なりの選択の基準をもとう
現代は、健康ブームといわれています。
生活習慣病の危険が高くなる高齢者や中高年はもちろん、20~30代の若い世代、ときには小・中学生までもが「健康によい食品」を求めています。

健康に良い食品とは?
自分や家族にとって、どういったものが「健康によい」のかは、一人ひとり違います。
たとえば、カリウムのとりすぎは腎臓に悪いといっても、腎臓病ではない人はそれほど神経質になる必要はありません。
コレステロールが多い食品は、高血圧の家系の30代以上の人は、気をつけた方がいいでしょうが、育ち盛りの10代や新陳代謝がさかんな20代にはむしろ大切なものです。
自分や家族はどういう病気になりやすいか、どういう体質なのかをよく知ったうえで、どんな食品を求めるのかということが、まず重要です。
自分と家族のために選ぼう
味、栄養、健康によい、価格など、好みで選べる幸せな時代です。
何を優先するのかは一人ひとり、各家庭ごとに選ぶことができます。
「自分は、我が家は、こういう観点から食品を選ぶ」という選び方の視点をしっかり持ちましょう。

何事もバランスが大事
健康に良いものを食べるから健康になるのではありません、それを含めた生活の習慣で健康が維持できます。
食事、睡眠、運動などそれぞれに合ったバランスで暮らしたいものです。